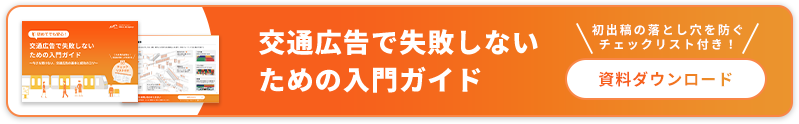ナレッジコラム つり革広告とは?電車内で視認性抜群の広告媒体の特長・活用法を解説
電車広告
2025.08.19
つり革広告は、電車内で目線に近い位置に掲出される広告媒体のひとつです。電車を利用する多くの人々が自然と目にするため、広告の視認性が高く、ブランドメッセージを効果的に伝えられる点が魅力です。
本記事では、つり革広告の基本情報から、メリット、注目事例、活用時の注意点まで詳しく解説します。電車広告の中でも印象に残りやすいメディアを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

つり革広告とは?視線を引きつける“目の高さ”メディアの特性
つり革広告とは
つり革広告は「アドストラップ」とも呼ばれ、電車内のつり革の握り手部分の上部に設置される広告です。つり革に手を添えるタイミングや、目の前に位置することで、自然と目に入りやすく、電車広告の中でも高い注目度を誇ります。広告サイズはコンパクトですが、その分、視線との距離が近いため、メッセージをダイレクトに伝えられる点が特長です。
【関連ページ】
つり革広告
つり革広告が持つ4つの魅力
・高い視認性
つり革広告は、目線の位置に広告クリエイティブがくることから、視認性が高く、訴求力が高いものが見込めます。一編成すべてのつり革に掲出することも可能です。
・メッセージの伝達に優れる
目の前でじっくり見てもらえることが多いため、短いキャッチコピーやキービジュアルを効果的に活用できます。商品名やサービス名、ブランドメッセージをしっかり伝える広告に適しています。
・反復効果がある
毎日の通勤・通学などで同じ路線・車両を利用する人が多いため、つり革広告を何度も目にすることで記憶に残りやすくなります。一定期間継続掲出することで、ブランドや商品を徐々に認知させる刷り込み効果が期待できます。
・規定の範囲内で形状の工夫も可能
鉄道会社の規定内であれば、つり革の形状を変更する広告展開も可能です。キャラクターの顔の形にしたり、ユニークな形で話題を呼んだりする施策も実施されています。形状の工夫により、さらなる注目を集めることができます。

インパクトのあるつり革広告事例
つり革広告は、車内の限られたスペースで乗客の視線をしっかりと捉えるため、クリエイティブの工夫や掲出手法によって大きな話題や訴求効果を生み出すことが可能です。ここでは、注目を集めた実際の事例を紹介しながら、その成功のポイントを解説します。
4路線ジャック施策でのパーソナルメッセージ展開
あるスムージーブランドは、東京メトロの4路線を活用し、つり革広告を含む電車内外の多種多様なメディアをジャックする大型プロモーションを実施しました。つり革部分には、乗客一人ひとりに語りかけるような短いメッセージを掲出し、日常の移動中にふと心が和らぐような演出を行いました。
この施策は、広告としての強いインパクトを残しながらも、ブランドが目指す親しみやすさや信頼感を伝えることに成功しています。
成功のポイント:
マス向けの展開でありながら、1対1のパーソナルコミュニケーションを意識したメッセージ設計が功を奏しました。また、視認性が高いつり革広告の特性を活かし、印象的なコピーを目立たせることで共感や話題性を生みました。
【関連ページ】
【メトロアドレビュー】VOL.22 ビタミン色の「ハロー」であいさつ。 通勤・通学も楽しく元気になっちゃう電車。

つり革広告を利用する際の注意点
つり革広告は効果的な車内メディアである一方、掲出や制作にあたっては特有の注意点があります。事前に確認しておくことで、無駄なコストやトラブルを避け、より高い広告効果を目指すことができます。
広告サイズが小さいため工夫が必要
つり革広告は、他の電車内広告と比べて掲出スペースが限られています。たとえば東京メトロでは、四角柱型のつり革に縦105mm×横126mmの広告を巻き付ける形式になっており、正面から見える面積はさらに小さくなります。限られたスペース内で、いかに印象的に伝えるかを考えたデザイン設計が重要です。
鉄道事業者や路線の車両によって形状やサイズが異なる
つり革の形状は路線や鉄道事業者によって異なり、四角柱型・円柱型・楕円型などがあります。それぞれに応じたデザイン調整が必要なため、事前に掲出先の車両仕様を確認しておく必要があります。
1編成ごとの掲出が基本
首都圏の電車は1編成5-11両などで運行していますが、つり革広告の掲出単位は基本的に1編成ごととなります。例えば、つり革広告をJR山手線で大々的に掲出したい場合も、一日の40編成以上もの編成のうち1編成のみとなります。広告効果を考え、複数編成に出すことも検討しましょう。
制作費がかさみやすい
つり革広告は、1車両あたりにつり革が複数個あり、それが10両分となれば100を超える枚数を出稿する必要があります。そのため、制作費がかさんでしまうこともあるため、全体の費用が予算オーバーとなってしまう恐れがあります。広告料金はもちろん、制作費についてもあらかじめ見積もりを正確にとっておきましょう。
形状変更の制限がある
一部の事例では、つり革の形状をキャラクターの顔や商品イメージに変えるような演出も見られますが、日本では安全基準上、大幅な改変は制限されています。派手な造作や特殊な装飾を検討する場合は、必ず事前に鉄道事業者と確認を取りましょう。

まとめ
つり革広告は、視認性が高く、乗客の目線に近い位置でメッセージを伝えられることから、電車内広告の中でも高い訴求力を持つ媒体です。スペースが限られているためクリエイティブには工夫が必要ですが、その分、1対1のコミュニケーションに強く、印象に残りやすいという特性があります。
また、車内全体を活用したジャック施策や、Web誘導・SNS拡散といった他のプロモーション手法との連動によって、つり革広告の効果をさらに高めることが可能です。
広告の規模や目的、ターゲットに応じて、最適なデザイン・路線・掲出方法を選び、ブランドやサービスの魅力を最大限に伝えていきましょう。
つり革広告をご検討の際は、ぜひお気軽にアドターミナルまでご相談ください。