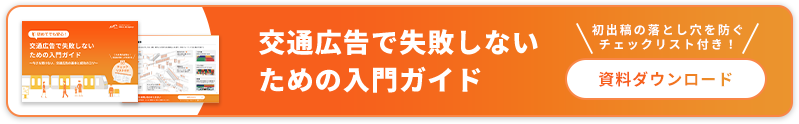ナレッジコラム 交通広告の効果測定ガイド~今すぐできる分析方法から未来の動向まで解説
電車広告駅広告
2025.04.09

目次
交通広告は本当に見られているのか?
駅構内の大型ビジョンや車両内のポスターなど、街を行き交うときに自然と目に入ってくる交通広告。しかし、「どのくらいの人が本当に見ているのか?」という点が曖昧だと感じる方も多いのではないでしょうか。
このような背景から、OOH(交通広告・屋外広告)業界では、広告の視認状況をより正確に把握するために、メディア視聴者のデータを数値化し、定量的・定性的な指標を導入する動きが進んでいます。 広告主が確かな根拠をもとにメディアプランを立てられるよう、効果測定の仕組みが強化されつつあるのです。
昨年2024年7月には、日本の主要な広告会社や媒体社が集結した「日本版OOHメジャメント標準化検討準備委員会」から、RFP(提案依頼書)1.0版(https://www.jaaa.ne.jp/ooh_2407/)がリリースされました。ここでは、2025年度中をめどに「日本版OOHメジャメントおよびその計測システム」を立ち上げようという計画が提示されています。
本記事では、以下の点を詳しく解説します。
そもそもなぜ、交通広告で「媒体価値の標準化」が必要なのか?
業界が構築を目指す「日本版OOHメジャメントおよびその計測システム」とは?
この新しい仕組みが広告主や初心者にとってどんな価値をもたらすのか?
なぜ交通広告の効果測定が求められるのか?
駅ポスターや車内ディスプレイなど、交通広告の魅力は「移動中に自然と目に留まりやすい」「場所の特性を活かした訴求ができる」といった点です。しかし、テレビCMのGRP(延べ視聴率)やWeb広告のimp(広告表示回数)のように、明確に「これだけの人数が見ました」と示せないケースが多いのが現状です。
例えば、駅や電車の利用人数を参考にしながら効果を推定する手法もありますが、当然曜日や時間帯によって人の流れは変化します。また、そもそも乗降者数イコール視認者数とは限りません。AIカメラや各種センサー、人力での通行量調査など、各社が独自の算出をすることで比較がしづらく、「広告の効果を数値で示してほしい」という広告主のニーズに十分対応できていない課題がありました。
2020年、新型コロナウイルスの感染拡大により、人々の移動が大幅に制限されました。特に都市部では「ステイホーム」の影響で外出する人が激減し、これまで安定していた交通広告の視認状況が大きく変わりました。
その結果、「広告の定価はこのままで適正なのか?」という疑問が広告主の間で高まり、出稿を見送るケースが増加し、より正確な視認データを数値で示す必要性が強く認識されるようになりました。
この流れを受け、交通広告業界では、広告の視認率や効果を客観的に測定し、透明性の高いデータに基づいた広告プランニングができる仕組みづくりの必要性が顕在化し、 業界全体で「広告の価値を可視化する」標準化の動きが本格化することとなりました。
交通広告の効果測定の具体的な手法
交通広告の効果測定は、Web広告と違い、クリック数などの明確な指標がないため難しく感じられます。しかし、実際には様々な手法を組み合わせることで、広告の費用対効果を客観的に評価できます。主な測定手法は次の通りです。
インターネットリサーチ(アンケート)
広告掲出前後にWebアンケートやインタビューを実施し、「広告を見たか」「印象に残ったか」「広告に好感を持ったか」など認知や態度の変化を聞き取ります。回答データから広告到達率やブランド認知の変化を推定でき、ユーザーの心理や感想といった定性的情報も取得できます。
行動ログ・位置情報データの活用
スマートフォンのGPSや携帯電話基地局データを用いて人流分析を行い、広告掲出エリアにどれくらいの人が滞在していたか、その後の行動(店舗への来店など)を客観的に把握します。広告接触者と非接触者の来店率やWeb行動の差を比較することで、広告が行動変容に与えた影響を検証します。
視線評価やSNS解析などの補助手段
AIカメラやアイトラッキング調査によって広告への視線の集まり具合を確認したり、広告掲出前後のSNS投稿数や検索ボリュームの変化を計測したりします。また広告にQRコードを掲載し、Webサイトへのアクセス数を計測することも補完的な指標になります。複数の手法を組み合わせることで、多角的に広告効果を検証し、次の施策に活かすことが可能です。
目的ごとの効果測定プラン
交通広告の目的は、ブランド認知の向上、来店・集客、特定ターゲット層のリーチなど様々です。目的に応じて選択すべき指標や検証方法が異なるため、広告掲出前に成功の定義を明確にし、適切な測定方法を設計することが重要です。
ブランド・認知
ブランドや商品の認知拡大を目的とする場合、広告の到達人数を示す指標や広告想起率・広告認知率が重要です。駅別の交通量やデジタルサイネージのコンタクト数はJAFRA共通指標などで推定でき、掲出後はインターネット調査でブランド認知や購買意向の変化を確認します。これらのデータを組み合わせることで、どの媒体が認知向上に寄与したかが明らかになります。
来店・集客
来店や集客が目的の場合は、来店者や実際の購買につながった数が重要な指標です。GPSデータによる行動ログ分析や店舗設置のQRコードの読み取り、Webサイトへのアクセス数を分析し、交通広告とその後の行動がどれだけ結びついたかを検討します。広告接触者の属性や時間帯を把握することで、次回のメディアプランに生かせます。
特定ターゲット層へのリーチ
特定のターゲット層へのリーチを目的とする場合は、ターゲットリーチ率を測定します。行動ログデータや媒体社独自のデータプランニングツールを活用し、ターゲット層が通りやすい駅や路線を選定します。掲出後にはインターネット調査やSNS分析でターゲットへの認知変化を検討します。
このように、目的によって指標や検証方法が異なります。広告を掲出する前に何を成果とするか明確に定義し、適切な計測手法を選択することが効果測定を成功させる鍵です。こうした計画を立てることで、より精度の高い投資判断が可能になります。
業界で構築を目指す「日本版OOHメジャメントおよびその計測システム」とは?
「日本版OOHメジャメント標準化検討準備委員会RFP1.0版」は、2025年度中に本稼働を目指す「日本版OOHメジャメントおよびその計測システム」を、どう構築するかの提案依頼書です。本内容から、今後交通広告の効果測定がどのように変わっていくのか解説します。
主なポイント
1. 交通広告や屋外広告、小売広告などのOOHメディア全般が対象である
2. 誰がどのくらい視認したかといった、広告の視聴数を「VAC(Visibility Adjusted Contact)」などの指標で計測
3. 広告主がデータを活用しやすいように、ダッシュボードやAPIを通じて提供
これにより「○駅のこの広告枠は、期間中におよそ○万人が視認したと推定できる」といったデータを根拠に、より公平かつ透明性の高い取引が可能になります。
発行元となる「日本版OOHメジャメント標準化検討準備委員会」は、広告会社6社と媒体社6社、さらにオブザーバー1団体という構成。日本の交通広告・屋外広告をリードするプレーヤーが集結しており、最終的にはこうしたデータを業界全体で共有・活用する「JIC(Joint Industry Currency)」の役割を担うことを目標にしています。

メジャメント標準化で提供される価値とメリット
広告主や代理店がデータを根拠にメディアプランを組みやすくなる
従来の交通広告では、「何人が広告を見たのか」を明確に示すことが難しく、広告主にとって投資対効果を判断しづらいという課題がありました。
しかし、今回の標準化により、テレビCMのGRPやWeb広告の表示回数と同様に、交通広告の視認数を数値で示せるようになります。
これにより、以下のようなメリットが期待できます。
✔ 社内稟議や予算申請がスムーズになる(データに基づく根拠を示せる)
✔ テレビ・Web広告と併せて、OOH広告もプランに入れやすくなる
✔ 精度の高いメディアプランを提案できる
例えば「○○駅の大型ビジョンに1週間掲載すると、VACベースで○万人が見込める」という説明があれば、データに基づいた広告戦略の立案や投資判断がしやすくなります。
今後、メジャメント標準化が進むことで、交通広告の信頼性が向上し、広告主がより効果的な広告展開を行いやすくなると期待されています。
媒体社の持つ埋もれた媒体の価値を数字で証明
これまでの交通広告では、主要ターミナル駅や人気路線に広告を出すことが効果的と考えられる傾向がありました。しかし、データを活用した新たな評価手法が進むことで、単なる利用人数だけでは候補に挙がりづらかった駅や路線でも特定のターゲット層に強く訴求できる」価値があることが明確化されつつあります。
例えば、メトロアドエージェンシーが提供する 「行動DNAアナライザー」(公式サイト)のようなデータ解析ツールを活用すれば、広告の接触データをより詳細に分析し、駅や路線ごとの特性を可視化することが可能です。
例えば東京メトロの南北線は、丸ノ内線や銀座線と比べるとどちらかというとマイナーな印象を持たれやすいですが、港区や目黒区などを結んでいるため高所得層や外資系勤務の方に訴求しやすい可能性があるのです。
また、広尾駅のように、乗降者数はそれほど多くなくても医療機関やインターナショナルスクール、富裕層向けレストランなどが駅周辺に集中している場合、特定層への訴求力が高いと考えられます。
これまであまり知られていなかった駅でも、緩やかな人の流れが何度もポスターを視認するなど、多様な可能性を数字で立証できるようになるのです。
このように、多種多様な駅や路線が、それぞれの持つ独自の特徴を活かしながら「どんな層が広告を目にするのか」をデータで証明できる時代になっています。広告主にとっては、従来の知名度に頼らず、ターゲットが確実にいる「本当に広告効果の高い場所」を見極めることが可能になり、より戦略的な広告展開が実現できます。
初めて交通広告を検討する方にとっての新選択肢
これまでの交通広告は、「とりあえずターミナル駅に広告を出せばいい」「主要な路線なら効果があるはず」といった感覚的な判断で選ばれることが多い傾向にありました。
しかし、データを活用した広告の可視化が進むことで、「どの駅や路線に、どんなターゲットが集まるのか」を数値で把握し、より精密な広告戦略を立てることが可能になっています。
今後の交通広告の進化ポイント
✔ 本当にターゲットが集まる駅や時間帯をデータで選定できる
✔ 複数の駅・路線をまたいで総リーチ数をシミュレーション可能
✔ プログラマティックOOH(自動取引)による柔軟な広告出稿が可能に
このように、より科学的なアプローチが可能になり、「あまり知られていない路線や駅だけど、実はうちのターゲットに合っている」と気づくキッカケが増えるかもしれません。
初心者にとっても、データを根拠に「ここなら試してみようかな」と思えるだけでも、心理的なハードルはかなり下がります。
交通広告の課題と今後の可能性
以上のように日本版のOOHメジャメント標準化の動きが進むことで、交通広告の効果をより正確に測定できるようになる一方で、改めて次に挙げられるような課題に直面することも考えていかなければなりません。
課題①│計測コストやデータ更新頻度
データの取得やセンサーの設置、解析ツールなどの導入によって、定期的にアップデートをかけ続けるにはコストも手間もかかります。業界全体でどこまで協力し合い、投資を進めるかがカギとなるでしょう。
課題②│媒体間の競争激化
交通広告の視認データが可視化され、各媒体の広告価値が数値で示されるようになると、広告主はデータをもとに広告枠を厳選するようになります。
その結果、視認率が低い媒体や効果の薄い広告枠は淘汰される可能性が高まります。ただ、そうしたフラットな比較をきっかけに新しい販売戦略や改善策が生まれる可能性もあります。
課題③│定性的な価値も考慮する必要
交通広告は「街に溶け込むことでブランド体験を高める」という定性的な価値も大きいです。数字による評価が主流になる一方で、広告のクリエイティブや空間演出の力をどう維持・強化していくかが重要になります。

交通広告の未来
前述の課題を克服することで、OOH広告はテレビ・Web広告と並ぶ「第3のメディア」として、さらに存在感を増していくと考えられます。
特に、以下の2つの進化が今後のOOH市場に大きな影響を与えるでしょう。
①インプレッション課金型のDOOHの普及
デジタルサイネージを使い、「実際に見られた分だけ課金する」というモデルが日本でも徐々に導入され始めています。視認指標の整備が進めば、こうした取引形態が一気に普及する可能性があります。
②クロスメディアのプランニング
交通広告の数値データがテレビやWeb広告と同レベルで並べられれば、複数メディアを掛け合わせた総合的なメディアプランがより描きやすくなるでしょう。
またOOHは空間演出や街を彩るクリエイティブで話題化する力が強いことも、クロスメディアの一翼として評価が高まりそうです。
交通広告の未来は"のびしろ"しかない
「日本版OOHメジャメント標準化」の動きは、広告主がより安心して投資できる環境を整えるだけでなく、交通広告そのものの価値を飛躍的に向上させるきっかけとなるでしょう。
今後、視認データの透明化により、広告主はより戦略的な広告出稿が可能になるでしょう。 さらに、「駅広告が本当にターゲットに届いているのか?」を数値で判断できるようになるため、これまで埋もれていた「狙い目の駅・路線」が発掘される可能性もあります。
また、デジタルサイネージやプログラマティックDOOHなど、これからの交通広告は技術的にも運用面でも進化が期待されています。
街というリアルな空間の魅力と、数字という根拠が掛け合わさることで、OOHはさらに多彩な役割を担うでしょう。「場所ならではのインパクト」と「定量化された効果」の両方を活かす時代は、もうすぐそこまで来ています。
効果測定・KPI設計についてはこちらも参考にしてみてください
リードナーチャリング失敗事例から学ぶ成功の秘訣