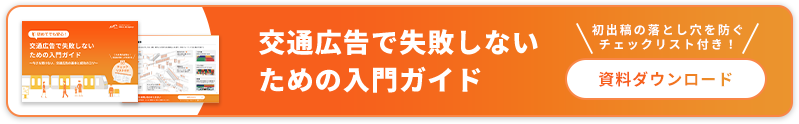ナレッジコラム 交通広告はどのようにしてプランニングされるのか?~効果的なメディアプランニングの7ステップ~
電車広告駅広告
2025.04.23
交通広告は、どのような流れでメディアや掲出場所をプランニングしていくのでしょうか。交通広告のメディアプランニングの流れを7つのステップに分けて解説します。

目次
はじめに
「はじめての交通広告で避けたい失敗例と対策~成功に導くための10のチェックリスト~」では、交通広告の初出稿でありがちな失敗例を取り上げました。
では実際に、どのような流れでメディアや掲出場所をプランニングしていくのでしょうか。本記事では、はじめての方でもイメージしやすいように、交通広告のメディアプランニングの流れを7つのステップに分けて解説します。
ターゲット設定から効果測定までの全プロセスを整理し、他の広告施策と連携させるポイントや、広告効果を最大化する工夫もご紹介します。
交通広告のプランニングはこう進める!基本の流れを押さえよう
交通広告を効果的に活用するには、自社の目的やターゲット像を正しく設定し、それに合った駅や路線、掲出媒体を選ぶことです。
また、交通広告はWeb広告やテレビCMと異なるスケジュールを踏まえ、審査や入稿の流れを把握しておく必要があります。
この流れを事前に把握しておかないと、「希望の広告枠が取れなかった」「審査でNGになってしまった」などのトラブルにつながる可能性があります。
それでは、具体的にどのようなステップで進めればよいのか?
ここから、交通広告のメディアプランニングの基本ステップを詳しく解説していきます。
交通広告のメディアプランニング │ 7つのステップ
1. 目的とターゲットを明確化する
「何を目的として広告を出すのか?」を明確にしましょう。
✔ ブランド認知度の向上(広く多くの人に知ってもらう)
✔ 新商品・キャンペーンの告知(期間限定のプロモーションを最大化する)
✔ 採用活動・企業PR(特定のターゲット層に訴求する)
ターゲットが明確でないと、駅やメディアを決める際に遠回りになりがちです。ターゲットの年齢層・職業・ライフスタイルを分析し、適切な広告配置を計画しましょう。
2. ターゲットの行動導線をリサーチする
「ターゲットがどこで広告に接触するか」を考えることが重要です。
✔ 平日・休日の移動パターンを調査する
✔ 通勤・通学・買い物など、ターゲットの利用路線を把握する
✔ 特定の時間帯に広告が目に入りやすい場所を検討する
例えば、ビジネスパーソン向けなら都心部の主要駅・オフィス街、学生向けなら大学の最寄駅などが適しています。
3. 掲出期間や予算を設定し、優先順位を考える
「いつ・どのくらいの期間掲出するか?」を事前に決めましょう。
✔ 短期プロモーションか、中長期のブランディングかを明確にする
✔ 繁忙期やイベントシーズンを意識して掲出期間を決める
✔ 広告予算内で最大限の効果が出せるメディアを選ぶ
予算に応じて、交通広告以外のWeb広告やSNS広告施策などを組み合わせると、さらに効果的なケースもあります。
広告予算や期間設計は、事業の短期・中期計画とセットで考えると整理しやすくなります。短期経営計画書/中期経営計画書の基本的な考え方は、こちらも参考になります。
参考:短期経営計画書と中期経営計画書の作り方や立て方
4. 駅構内メディアか車両メディアか、それぞれの特色を理解する
✔ 駅広告 → 改札周辺・ホーム・コンコースなどでエリア特性を活かしたインパクトのある表現ができる
✔ 電車広告 → 移動中の乗客が長時間目にしやすく、繰り返し訴求できる
例えば、短期間で大きなインパクトを狙うなら「大型駅ポスター」、じっくり伝えたいなら「車内広告」が適しています。
5. クリエイティブとの相性を確認しながら枠を選ぶ
「広告のデザインが、掲出場所と合っているか?」をチェックしましょう。
✔ ポスター広告なら「遠目でも読める」デザインにする
広告のサイズや視認性を考慮し、最適なクリエイティブを設計することが成功の鍵です。
6. 審査スケジュールと入稿期限を把握する
交通広告には厳格な審査基準があるため、スケジュール管理が重要です。
✔ 広告表現のNG要素(医療関連・過度な表現など)を確認する
✔ 媒体ごとの入稿スケジュールを押さえ、余裕を持ったスケジュールを組む
審査基準に違反すると、修正対応に時間がかかり、掲出が遅れるリスクがあります。
7. 掲出開始後は効果測定の方法を準備する
「広告効果をどのように測るか?」を事前に考えておきましょう。
✔ 交通広告掲出期間のHPへのアクセス数を測定する
✔ SNSキャンペーンと連携し、話題化を図る
✔ アンケートや来店データを活用し、ブランドリフトを分析する
広告掲出後は、効果測定を行い、次回の改善ポイントを洗い出すことが重要です。
このように、目的とターゲットを最初に明確化しないと、駅や路線を決める段階で遠回りになることが多々あります。また、ここで設定した期間や予算の範囲内で現実的な枠を探していくのもポイントです。
ただし、これらの基本ステップを押さえた上で、さらに広告効果を高めるための「戦略的な選び方」や「他メディアとの連携」も重要になります。
ここからは、より効果的な交通広告の運用を実現するための具体的なコツを紹介していきます。
【関連リンク】
交通広告の新たな効果測定ガイドラインを徹底解説!
交通広告の効果測定はどうする?実施方法から次に活かす方法まで解説!
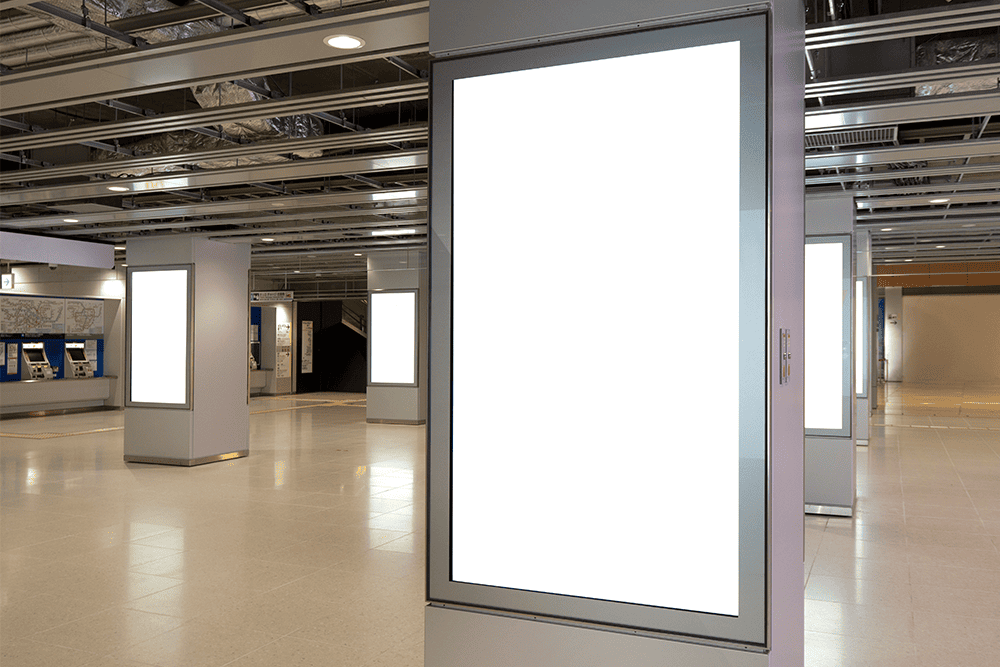
媒体選定のコツ
駅構内メディアと車両メディアには、それぞれ異なる特徴があります。駅構内のポスターやデジタルサイネージは大きく視認性が高いというメリットがありますが、ターミナル駅などは人気が高く、早めに枠が埋まりやすいという難点もあります。
一方、車両内の中吊り広告やドア横ポスターは、乗客が一定時間とどまる空間で繰り返し目に触れてもらえるものの、混雑時には読みにくい場合もあり、デザインや文字量のバランスを考える必要があります。
選定の際には、想定するターゲット層が多く利用する路線や駅をどのように乗り継いでいるかを把握したり、利用者数だけでなく利用者の属性まで考えたりするのがおすすめです。駅や路線ごとのデータは、広告代理店や媒体社を通じて入手できる場合もあるため、早めに相談してみると良いでしょう。
他メディアとの連動で相乗効果を高める
交通広告単体でも一定の効果が期待できますが、オンライン広告やテレビCMと組み合わせることで接触回数を増やし、より記憶に残りやすくする方法があります。たとえば、駅でポスターを見かけた人がスマートフォンで検索したときに、同じブランドのWeb広告が表示されると「また見た」という意識が生まれ、深い認知に繋がりやすくなります。
ただし、他メディアとの連動を行う際は、「いつ」「どこで」「どんな切り口で」接触するのかを整理して、混乱させないようにメッセージを統一することが大切です。制作物のトンマナがバラバラだと、せっかくの相乗効果が薄れる原因になります。
他メディア連動はWeb広告だけでなく、オウンドメディアなどのコンテンツマーケティングで“検索される理由”を蓄積しておくと、指名検索・検討促進までつながりやすくなります。(参考:コンテンツマーケティングのメリット・デメリットと、成功の秘訣)
効果を最大化するための工夫
交通広告は、視認する時間が限られているため、短くシンプルなメッセージが基本です。一般的に、普段の移動中に触れるOOHメディアの接触時間は数秒と言われ、その中でも意識が集中するのは1秒未満ほんの一瞬です。
接触時間の比較的長い電車内ポスターなどであればある程度の情報量を入れ込むこともできますが、それでも文字が小さすぎると一瞬で読み飛ばされてしまいます。
また、駅ジャックや車両ラッピングのように大規模に展開するとSNSで話題になりやすいですが、その分費用がかさむので、狙いと予算の兼ね合いを見極める必要があります。
掲出後はSNSの写真投稿やWebサイトのアクセス推移などを踏まえて、効果測定を行うことも忘れないようにしましょう。短期間で判断せず、ある程度継続して出稿しながら反応を確かめると、認知拡大がじわじわと進んでいる実感が得られることがあります。

最終的にはプランニングの専門家に相談を
交通広告の実施を決めたら、早い段階で交通広告に精通した専門家へ相談するのがスムーズです。メディア選定だけでなく、審査手続きや入稿スケジュール、さらにはクリエイティブの調整に至るまで、媒体社とのやり取りをトータルサポートしてもらえます。特に交通広告をはじめて出稿する方なら、まずは比較的低予算での簡単な枠を使ったテスト出稿から始め、効果を見極めて次のステップに進むと良いでしょう。
おわりに
交通広告をプランニングするには、目的・ターゲット設定から媒体選定、スケジュール・審査など多岐にわたる要素を管理しなければなりません。
オンライン広告と違って物理的な枠が限られているうえ、掲出作業や審査に時間がかかるため、事前準備をしっかりしておくことが重要です。他メディアとの連動を含めて計画を立てると、交通広告が持つ公共性・信頼感と合わせて相乗効果を得られるでしょう。