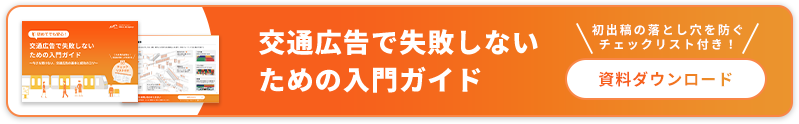ナレッジコラム 効果的な交通広告プランニングに欠かせないデータ活用術とメディア選定のコツを徹底解説!
電車広告駅広告
2025.05.26
交通広告の効果を最大化するには、データ活用と戦略的なメディア選定が欠かせません。本記事では、実際のプランニング現場で使われるデータやツールをもとに、効果的な広告展開のコツを詳しく解説します。

はじめに
私たちが毎日目にする駅構内の大型ポスターや電車内の広告。こうした交通広告は偶然その場所に掲出されているわけではなく、緻密なデータ分析に基づいて配置されています。こちらの記事で述べたようなOOH業界全体でのメジャメント(効果測定)の整備が進む一方で、各広告会社は独自のデータやツールを駆使し、交通広告への知見を活かした精緻なプランニングを行っています。
本記事では、交通広告のプランニングの現場で実際に使用されているデータやツールを紹介するとともに、具体的なケーススタディ、現在のデータ活用における課題、そして今後の展望について解説します。これから交通広告を検討する企業担当者や店舗オーナーの方々にとって、効果的なメディア選定の一助となれば幸いです。
交通広告プランニングの基本的な流れ
交通広告のプランニングは、大きく分けて3つのステップで構成されます。
1. 目的とターゲットの設定
まずは広告の目的を明確にし、「誰に」「何を伝えるか」を定めることが重要です。交通広告は、インターネット広告と比較するとターゲティングが難しいメディアといわれますが、データを活用することでターゲット層が多く利用する駅や路線を特定することが可能です。
主な目的の例
・ブランド認知向上
・新商品・キャンペーン告知
・採用PR・企業ブランディング
交通広告は、特に東京メトロのような都心ネットワークでは1日600万人以上のリーチを持つ「準マスメディア」としての特性があり、幅広い層への接触が期待できます。一方で、最近ではメトロアドエージェンシー社が提供する「行動DNAアナライザー」のような行動データ分析ツールにより、エリアターゲティングの精度も向上しています。例えば、「旅行好き」「映画鑑賞が趣味」「ビジネスパーソン」など特定の属性を持つ利用者が多い駅や路線を選定することが可能になっています。
2. データに基づくメディア選定
ターゲットと目的が決まったら、次に具体的な媒体(駅・路線・広告枠など)を選定します。この際、以下のようなデータとツールが活用されます。
・各駅・路線の乗降人員データ(各電鉄発表)
・駅周辺の施設データ(JAFRA発表)
・アスキングベースの消費者データ
・「行動DNAアナライザー」などの位置情報データ
・競合出稿状況データ
例えば、旅行系サービスを展開する企業が「旅行好き」に訴求したい場合、対象層が多く利用している駅を特定し、そこでの掲出枠を優先的に検討します。
フィールドマーケティングシステムズ の「おススメの販促会社/SP会社まとめ」に当社が紹介されました。
3. 効果測定手法の設計
プランニングを進める段階で、あらかじめ「どのように広告効果を測定するか」を設計しておくことが重要です。交通広告の効果測定には、以下のような手法が活用されています。
・Webアンケートを活用した認知度調査
・行動データ(GPSなど)による人流分析
・SNSでの話題化状況のソーシャルリスニング
・Webサイトへのアクセス分析
・店舗への来店数の計測
効果測定の設計により、広告実施後の成果が客観的に評価できるようになります。
【関連リンク】
交通広告の新たな効果測定ガイドラインを徹底解説!
交通広告の効果測定はどうする?実施方法から次に活かす方法まで解説!
プランニングで活用されるデータとツール
●駅・路線ごとの利用者数・属性データ
交通広告のプランニングでは、まず基本となるのが「駅や路線の1日あたりの利用者数(乗降人員)」です。さらに「ビジネスパーソンなどの利用割合」も重要な判断材料となります。
例えば、東京メトロ南北線は、利用者数こそ他路線に劣るものの、港区や目黒区などを結んでいるため高所得層が多いことが推察できます。
●シミュレーションツール
交通広告のプランニングにおいては、電鉄各社が公表している駅・路線ごとの利用者数データや、特定ターゲット層の行動傾向を基にしたシミュレーションにより、媒体ごとの想定接触者数を算出するのが一般的です。
さらに、日本鉄道広告協会(JAFRA)が実施する共通指標調査で得られる「広告到達率」※1を掛け合わせることで、広告が実際に視認される可能性の高い“推定接触者数”をより精緻に見積もることができます。
メトロアドエージェンシーでも、このJAFRAの共通指標に基づく広告到達率データを用いて、車内メディアをはじめとする各媒体のリーチを客観的に評価しています。こうした定量的なデータを活用することで、広告効果のシミュレーションやプランニングの精度が高まり、より効果的な媒体選定につながります。
●位置情報を活用したリアル行動データ
最近では、「行動DNAアナライザー」のような位置情報データを活用したツールも交通広告のプランニングに取り入れられるようになってきました。これにより、「どのエリアの、どのような属性の人が、どの駅をよく利用しているか」といった行動パターンを可視化でき、より緻密なターゲティングが可能になります。
具体的な事例とプランニング例
●航空会社のキャンペーン事例
目的: 海外旅行に関心のある層への訴求
使用データ:アスキングベースの消費者データ、共通指標の広告到達率
プランニングの流れ:
①アスキングベースの消費者データを活用し、「過去1年間に海外旅行をした」「海外旅行に今後も行きたいと思っている」などの条件に合致する人々の利用駅を抽出。
②新宿、東京、渋谷、横浜など、上位にランクインした駅を中心に、予算内で最大リーチが可能なメディアを選定。
③キャンペーン期間に合わせた掲出スケジュールを設計
アウトプット例: 海外旅行関心層の利用が多い主要駅で広告を展開し、ターゲットの移動導線に沿った接触機会を最大化。効果的なエリアマーケティングを実現しました。
レポーティングの流れとデータ活用
交通広告のプランニングと同様に、効果測定(レポーティング)にもデータが重要な役割を果たしています。
共通指標に基づくインターネットリサーチ
現在、交通広告の効果測定では、日本鉄道広告協会(JAFRA)が定めた業界の共通指標に準拠したインターネットリサーチが一般的です。
具体的には、広告掲出期間中にそのエリアや路線を利用した人をスクリーニングし、実際に出稿された広告を見せて「見た」「見た気がする」「見ていない」などの質問を行います。「見た」「見た気がする」と回答した人の割合を「広告到達率」として測定し、これを基に効果を分析します。
認知獲得効果の測定
交通広告の大きな強みとして、新規の認知獲得効果があります。調査の際には、「この広告を見る前から知っていましたか?」といった質問を追加することで、広告によって初めて知った人の割合を測定できます。
実際にメトロアドエージェンシーが行った調査では、交通広告を通じて「初めて知った」と回答する割合が高く、新規認知獲得において一定効果が見られるケースもありました。特に、新サービスや新商品の認知拡大を目的とした施策において、交通広告は非常に有効な手段といえるでしょう。
SNS拡散による二次効果の測定
最近の交通広告では、SNSでの話題化による二次効果も重要視されています。メトロアドエージェンシーのコラム「拡散事例から学ぶ!SNSでも話題化する交通広告の活用術とは」※2でも紹介されているように、印象的な広告は利用者がSNSで写真を投稿することで、駅に訪れていない人にも情報が拡散します。
例えば、東京メトロでの車両ラッピングやステーションジャックなどの大規模展開は、SNSで話題になりやすく、直接接触した人数以上のリーチを獲得できる可能性があります。こうした効果は、ソーシャルリスニングツールなどを活用して測定・分析されます。

今後の展望と可能性
交通広告のデータ活用は、今後ますます進化し、より高度で効果的なマーケティング戦略の実現に貢献していくと予想されます。ここでは、今後の注目すべき方向性と期待される進化について解説します。
効果の可視化とメジャメント(効果測定)の高度化
今後の最重要課題の一つは、「交通広告の効果をより明確に数値化すること」です。現在も日本鉄道広告協会(JAFRA)などによる共通指標の整備が進められていますが、今後はさらに精緻で客観的な評価指標が求められます。媒体社や関連企業と連携し、統一的かつ信頼性のある効果測定システムの構築が加速していくでしょう。
クロスメディア効果の測定
近年では、交通広告だけでなく、テレビCMやWeb広告との組み合わせによる相乗効果の測定も注目されています。メトロアドエージェンシーでは、Web広告と交通広告の組み合わせによる効果測定の取り組みも行っており、統合的なクロスメディア分析により、メディアミックスの最適化が可能になります。
SNSでの話題化と副次的効果の定量化
交通広告の大きな特徴として、「面白くてシェアしたくなる」という側面があります。メトロアドエージェンシーのコラム「SNSでの話題化を見据えたOOHプランニングのすすめ」※3でも紹介されているように、インパクトのあるクリエイティブや斬新な掲出方法により、SNSで話題になり拡散されることで、直接接触した人以外にもリーチが広がる可能性があります。
例えば、インパクトのある駅空間ジャック広告のSNS拡散を促すために、SNS公式アカウントでの投稿を行なったり、ニュースに取り上げてもらうためのPR活動を行なったりといった話題性を重視した企画も増えています。こうした二次効果を含めた総合的な効果測定が今後の重要なポイントとなるでしょう。
参考:プロモーションの5つの手法とは?|ゴーアヘッドワークス
信頼性・安心感の数値化
交通広告ならではの「信頼性」や「安心感」という価値は、定量化が難しいものの、ブランド価値向上に大きく寄与します。公共交通機関の広告は、その場所柄から一定の信頼性が担保されており、特にブランディングを重視する広告主にとって大きな魅力となります。
こうした定性的な価値も何らかの形で可視化できれば、交通広告の真の価値がより明確になるでしょう。
まとめ
交通広告のプランニングでは、乗降者数や利用者属性、行動データなど、さまざまな種類のデータが活用されています。これらを組み合わせて分析することで、目的やターゲットに合ったメディア選定と広告戦略の最適化が可能になります。近年では、業界全体でのメジャメント(効果測定)標準化の動きも進んでおり、今後はより精緻な効果測定が可能になると期待されています。また、SNSでの話題化や信頼性といった交通広告ならではの価値も、定量的に評価される時代が到来しています。
交通広告の選定において重要なのは、単に「人が多い駅」を選ぶのではなく、目的やターゲットに合わせた戦略的なメディア選定です。本記事で紹介したデータやツールを参考に、より効果的な交通広告プランニングに役立てていただければ幸いです。
参考リンク
より詳しい情報については、以下のリンクも参考にしてください。
メトロアドエージェンシー コラム
※1 意外と知られてない!?交通広告を数字で測る方法とは? ~交通広告に関する指標データについて~
※2 拡散事例から学ぶ!SNSでも話題化する交通広告の活用術とは
※3 SNSでの話題化を見据えたOOHプランニングのすすめ