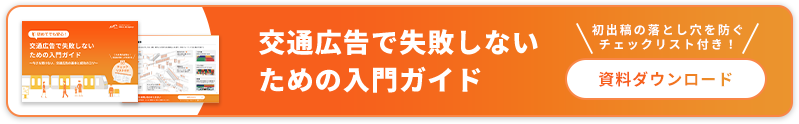ナレッジコラム 交通広告の効果測定はどうする?実施方法から次に活かす方法まで解説!
電車広告駅広告
2025.06.23
交通広告を出稿する際にはどれほどの効果が期待できるのかを検討しますが、そもそも効果はどのように測るのか、不安になっていませんか?すでに交通広告を手掛けており、その効果測定に頭を悩ませている方も多いでしょう。
今回は、現在、行われている交通広告の効果測定の方法と、効果測定後にその結果を次の広告出稿などに活かす方法を具体例も交えてご紹介します。ぜひ参考にしてください。

交通広告の効果は測れる?従来の課題と背景
駅や電車など、街中でよく見かける交通広告。これは「OOH(Out Of Home)広告」と呼ばれる屋外広告の一種で、公共の場で広く人々の目に触れるのが特徴です。インパクトがあるぶん、「実際にどれくらい効果があったのか?」を知りたいという声も多くあります。
しかし、交通広告はインターネット広告のように「クリック数」や「コンバージョン数」が簡単に取れるわけではありません。そのため、昔から「効果をどう測るか」は業界共通の課題でした。
交通広告の効果測定は、古くから試行錯誤され、さまざまな手法が試され、主に次の方法で行われてきました。
輸送人員数や乗降人員数の計測
電車やバスの広告では、どれだけの人がその車両を利用したか(=輸送人員)を見ることで、広告が見られた可能性を推測していました。駅広告でも、乗降人員(駅を利用した人数)を参考にして掲出場所を選定したり、広告のリーチ数を推定したりしていました。
アンケート調査の実施
広告掲出の前後で、対象となる地域の人や通勤・通学者に対して、インターネットなどを使ってアンケートを実施します。「広告を見たことがあるか?」「どんな印象を持ったか?」といった質問から、広告の認知や印象度を把握する方法です。
ただし、これら従来の方法には限界がありました。
「その駅や電車を使った=広告を見た」とは限らず、見た後の行動(来店・購入など)まで把握するのは困難だったのです。
そこで現在は、テクノロジーの進化により 複数のデータを組み合わせた“新しい効果測定のかたち” が登場しています。次章では、実際に使われている測定手法について詳しく見ていきます。
現状の交通広告の効果測定方法
テクノロジーの進化により、交通広告の効果測定も年々進化しています。これまでの「駅の利用者数から推測する」ようなアナログ的な方法に加え、今では人の動きや視線をもとにした、より精度の高い測定が可能になってきました。ここでは、現在よく使われている代表的な効果測定の方法をご紹介します。
人流データ活用:スマホの位置情報を活用
近年、交通広告の効果測定で注目されているのが「人流データ」を使った分析です。人流データとは、あるエリアに“いつ・どんな人が・どれくらい訪れたか”を記録した情報で、スマートフォンのGPSやWi-Fi、ビーコン、街頭カメラなどから取得されます。
たとえば、ある駅の広告前を「平日夕方に20〜30代の会社員が多く通過している」といった具体的な数値で可視化できるようになります。これにより「広告を見た可能性のある人の数」や「その後のWebサイトへのアクセス数」「店舗来店数」などを紐付けて分析できるようになり、効果測定の信頼性が大きく向上しています。
インターネットによるアンケート調査
インターネットや現地で行うアンケート調査も、今なお広く使われている測定手法のひとつです。「広告を見たことがあるか?」「どのように感じたか?」といった認知や印象を測定することで、ブランドや商品の理解度、記憶への定着などが分かります。近年は、人流データと組み合わせて調査を行い、定量・定性的な分析を行うケースも増えています。
アイトラッキング調査
少人数の調査対象者にアイトラッカー(視線を追跡するメガネ型デバイス)を装着してもらい、駅構内を歩いてもらうことで、どの広告がどれくらい視線を集めているかを測定する方法です。
駅ばりポスターやデジタルサイネージ、柱広告など複数のメディアの中で、実際に「どれが視認されやすいのか」が明らかになり、より効果的な広告設置に活用できます。アイトラッキングは、広告の「設置場所」によってどれだけの注目を集めるかを事前に把握したい場合に有効です。
【関連リンク】
意外と知られてない!?交通広告を数字で測る方法とは? ~交通広告に関する指標データについて~
交通広告の新たな効果測定ガイドラインを徹底解説!

効果測定の結果をどう活かすか:次回の広告出稿に向けた評価と改善
交通広告の効果測定は、単にレポートを作って終わりではありません。得られたデータをどう読み解き、次回の広告戦略にどう活かすかが、費用対効果を最大化するうえで重要なポイントです。ここでは、効果測定結果の評価と活用の方法をわかりやすくご紹介します。
効果測定結果の評価方法
たとえばアンケート調査で「広告到達率」が分かった場合、それが高いのか低いのかを判断するには、比較が欠かせません。「広告到達率」とは、その広告を「見た」または「見た気がする」と回答した人の割合です。
この数値を既存の平均値や、同じ媒体・エリアで過去に実施された他の広告と比較すれば、今回の広告のパフォーマンスを客観的に評価できます。また、過去に自社で出稿した広告と比較することで、「掲出時期」「場所」「広告クリエイティブ」のどこに改善の余地があったのかも見えてきます。
人流データやアンケートから得られる「広告を見たあとの行動」も重要です。Webサイトの閲覧数や来店率の変化など、実際のアクションが増えているなら、広告による“態度変容”が生まれたと判断できます。
次回の広告戦略に向けた改善ポイントの明確化
測定結果を活かすためには、次回の出稿に向けて「何を改善すればさらに効果が出せるか」を具体的に考えることが大切です。
たとえば、
・駅ばりポスターよりデジタルサイネージの方が到達率が高かった → 媒体を見直す
・朝より夕方の時間帯の方が人流が多かった → 掲出時間を調整する
・特定の駅で認知効果が高かった → 集中的に掲出する
といった具合に、媒体選びやタイミングの最適化、クリエイティブ改善など、実践的な次の一手に結びつけることができます。
さらに、こうした分析結果は、社内での報告や意思決定材料としても活用でき、広告活動の透明性や納得感を高める効果もあります。

まとめ
交通広告の効果測定は、難しいイメージを持たれがちですが、今ではさまざまなデータや技術を活用することで、成果を“見える化”することが可能です。
そして、測定したデータは、次の広告プランに活かすための大切なヒントになります。出稿する路線や掲出場所、クリエイティブを改善することで、広告効果を着実に高めていくことができます。
交通広告の効果測定について「何を見ればいいか分からない」「次の出稿にどう活かせばいいか知りたい」とお考えの方は、ぜひメトロアドエージェンシーにご相談ください。
東京メトロを中心に、駅・電車など多彩な交通広告の取り扱いに加え、広告戦略から制作・効果検証まで一貫してご支援します。
まずはお気軽に、無料相談をご利用ください。交通広告のプロが丁寧にサポートいたします。